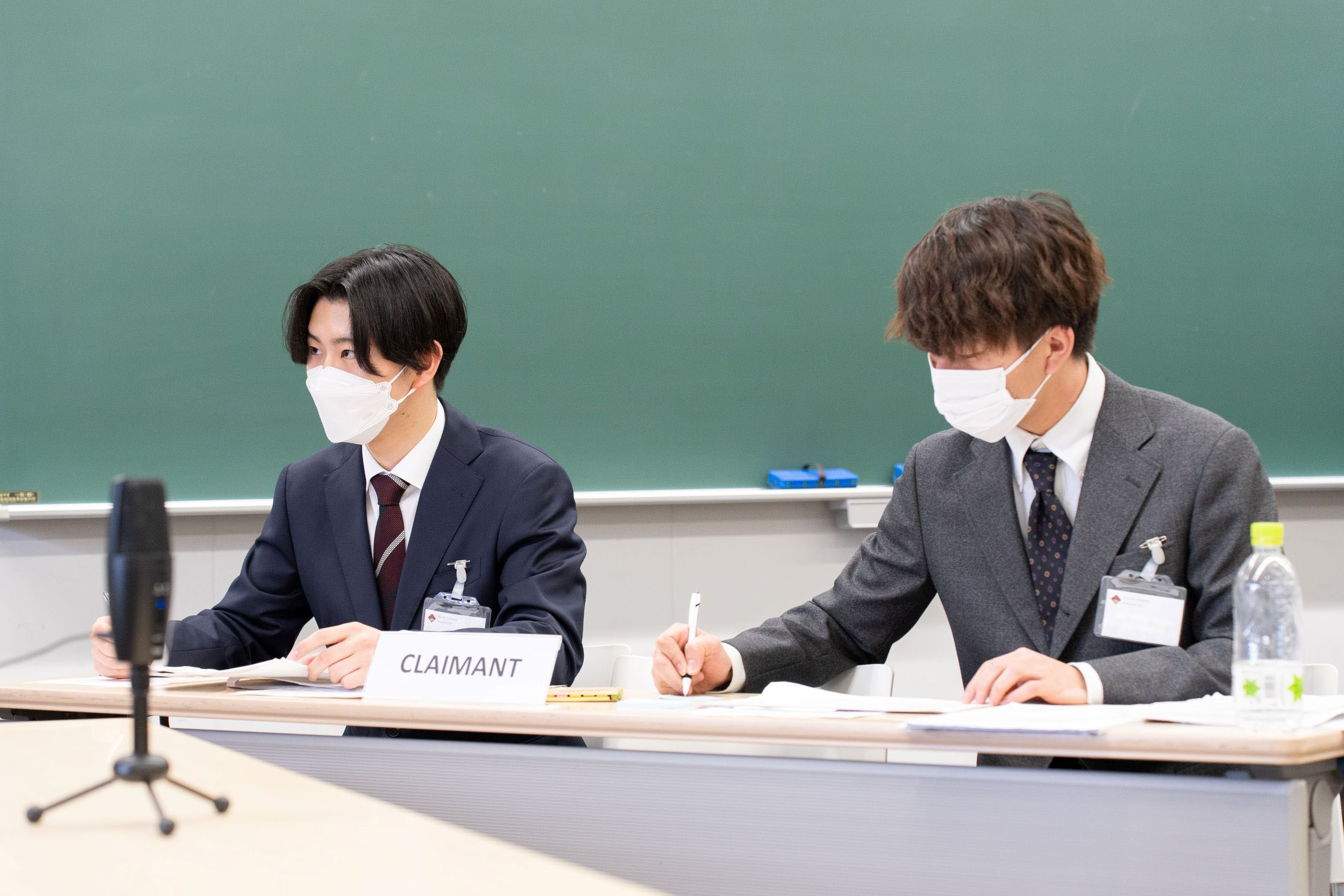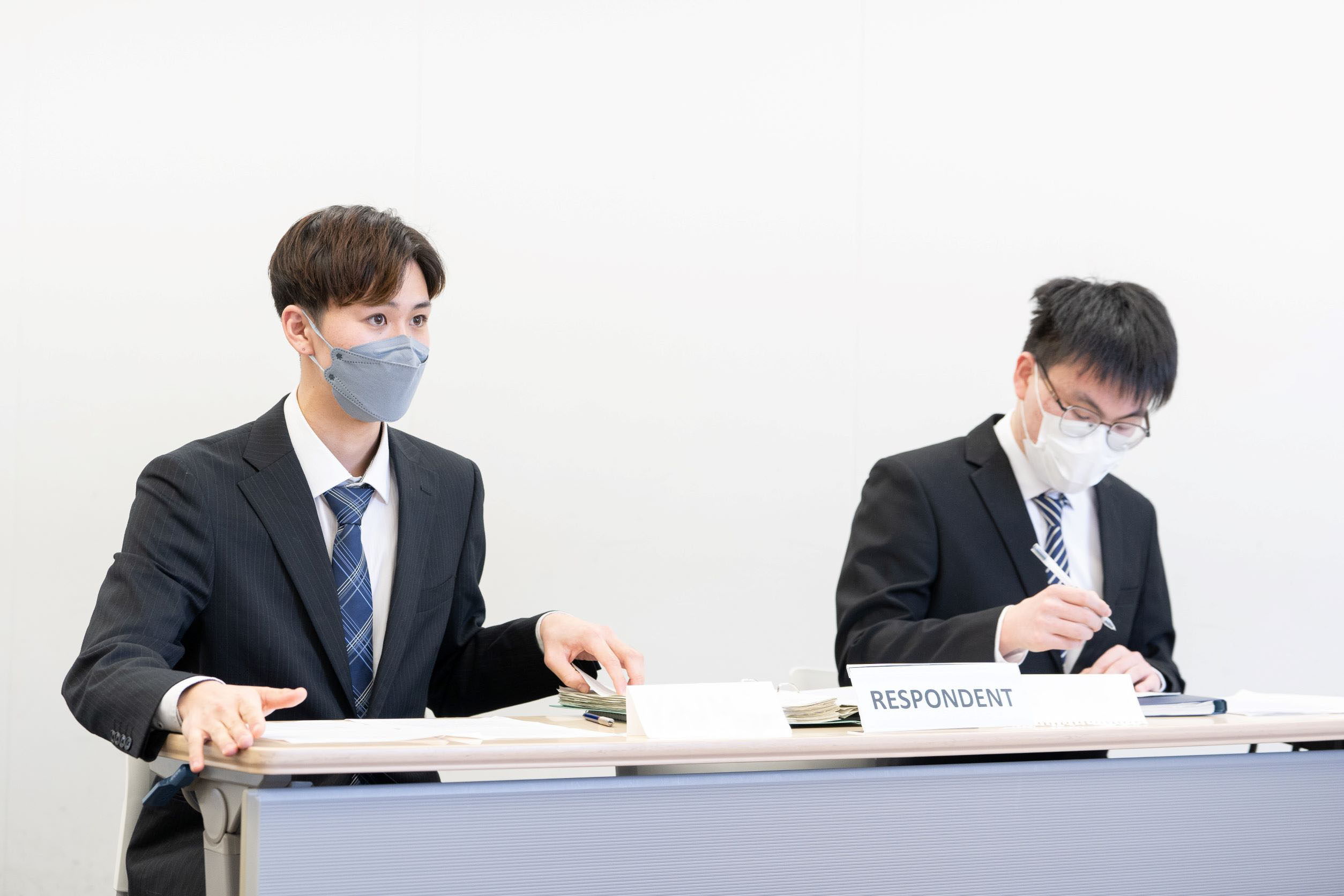すべての本大会とプレ大会(練習大会、プレムート)で同一の問題が使用されます。問題文の構成について、31st Vis Mootの問題を例に説明します。以下に出てくるページ番号は、この問題のページ番号です。
まず、4~18頁が仲裁を申し立てるにあたって申立人が提出した書面、19~28頁がICC(国際商業会議所。本件で利用される仲裁機関)からの連絡文書、29~36頁が被申立人が提出した書面、37~45頁がICCからの連絡文書となっています。さらに、申立人から追加の申立てがあり(46~50頁)、仲裁廷・ICCからの連絡(51~53頁)、被申立人からの反論(54~56頁)が続きます。以上の書面のやりとりと仲裁廷・当事者間の協議を経て、Procedural Order No. 1(58~60頁)が仲裁廷から出されています。なお、Procedural Order No. 2(61~66頁)は、次に説明するクラリフィケーションに伴い公表されるものです。
主に、仲裁申立書(Request for Arbitration)と証拠書類(Claimant Exhibit)から構成されます。当事者間の事実関係と請求・主張を把握するのに重要な文書となります。一連の文書の最初のページ(4頁)は、仲裁申立書や証拠書類を提出するにあたってのカバーレターとなっています。たいていの場合、仲裁廷を構成する3名の仲裁人のうちの2名については、各当事者が1名ずつ選任することになっており、これらの文書の中で、申立人が選任することとされている仲裁人1名が指名されています。
主に、答弁書(Answer to the Request for Arbitration)と証拠書類(Respondent Exhibit)から構成されます。これらも、当事者間の事実関係と請求・主張を把握するのに重要な文書となります。一連の文書の最初のページ(29頁)は、答弁書や証拠書類を提出するにあたってのカバーレターとなっています。たいてい、これらの文書の中で、被申立人が選任することとされている仲裁人1名が指名されています。
手続命令(Procedural Order)とは、仲裁手続の進め方に関する仲裁廷による指示です。Procedural Order No. 1には、次の期日(=大会)をどのように進めるかが記載されており、特に、主張書面(Memorandum)や口頭審理で議論すべき争点や、主張書面の提出締切りなどが指示されています(58~59頁、4(1)(2)段落)。また、問題に登場する架空の国の法律や判例に関する補足情報も書かれています(59頁、4(4)(5)段落)。